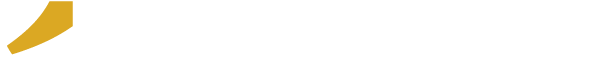資産運用 Lab.
第5章 志、初心
要約
本章では、村上ファンドの設立当初の動きについて書かれている。1998年8月から2002年12月迄の変遷である。
筆者によれば、この頃の村上ファンドは青かったが、純粋でもあった。村上には、はなからグレーな領域をついて金を儲けようという考えがあったのではない。村上ファンドは、日本を良くしたいという高い理念に裏打ちされてスタートした会社だったのだ。
青く、純粋な村上ファンドは、ITバブルが弾けた直後のこの時期、いくつもの挑戦をし、成功や失敗を繰り返して行く。
昭栄の敵対的TOB案件
1931年設立、もともとは生糸メーカーだった昭栄の実態は、芙蓉グループ系列の不動産管理会社だった。310億円もあるとされた土地の含み益に加え、602万株保有していたキヤノン株の含み益243億円も魅力的だった。
土地とキヤノン株だけで600億円近い価値があるにも関わらず、当時の昭栄の時価総額は100億円、総資産は190億円、株主資本は77億円。時価総額が解散価値を大きく下回っている典型例だ。
村上はこの乖離の大きさに目をつけて、昭栄の発行済み株式の100%(1400万株)の取得を目指した。村上ファンドの投資家であるオリックスはTOBに必要な資金141億円を全額融資する予定で、融資にあたっての担保は取得予定の昭栄株。つまり、この昭栄TOBは、買収予定の会社の資産を担保にして借入れをおこすLBO(レバレッジド・バイ・アウト)の走りでもあったのだ。
買い付け価格は1株1000円。800円台で低迷していた昭栄株の株価は、日本人同士で初めての敵対的TOBが話題を呼び買い付け価格を大きく上回る1480円まで跳ね上がった。
結果として、安定株主の富士銀行(現みずほ銀行)などはTOBに応じず、村上ファンドの株式取得はわずか6.52%にとどまった。村上ファンドの完敗。当時を知る某外資系金融期間の幹部は、TOB価格が低過ぎたと指摘する。
村上ファンドのデビュー戦は、ほろ苦いものとなった。
東京急行電鉄による東急ホテルチェーン子会社化案件
村上ファンドは東急電鉄と300万円でグループ戦略のコンサルティング契約を締結し、東急ホテルチェーンの完全子会社化を提案した。設立当初の村上ファンドは、コンサルティング業も拡大していく考えがあった。
東急ホテルチェーンは、名古屋、大阪、京都の各一等地にホテルを有する極めて資産リッチな会社であったため、買収される危険を避けるため、村上ファンドは完全子会社化を提案したのだ。
東急電鉄は結局この提案を実施し、東急ホテルチェーンの完全子会社化案件は、成功裏に終わった。
東京スタイル
2001年後半、村上ファンドはビッグディールを仕掛ける。東京スタイルである。村上自身が、ファンドの設立前から株主総会に出席するなどして調査に調査を重ねてきた銘柄である。
2002年1月、株主である村上ファンドは東京スタイルに対してそれまで1株あたり12.5円だった配当を500円に引き上げることを求める手紙を東京スタイルに提出。配当総額約500億円の根拠は、「余剰金500億円は不動産投資に充てる」という高野社長の発言であり、これに対して「本業に無関係で不慣れな不動産に投資するなら、株主に還元するべき」という主張をした。これにより、国内初のプロキシーファイトが勃発。
2002年5月の株主総会が決戦の舞台であるが、株主の票を巡って、高野社長と村上ファンドは戦いを続けた。事前の票読みでは村上ファンド・東京スタイル共38%程度で、22%の浮動票が勝敗を左右されると目されたが、ふたを開けてみればある程度の差がつき、村上の提案は全て否決。村上の敗北に終わった。
東京スタイルのプロキシーファイトは高くつき、弁護士を2人つけた他、株主探しの為の調査費用などで億単位のコストを支払った。
これらの例からもわかるように、青く、純粋な村上ファンドは、思うように案件を成就させることが出来なかったのである。