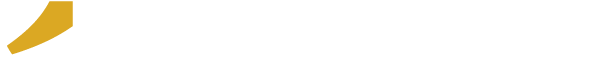資産運用 Lab.
第六章 遭遇のラスヴェガス
サブプライム業界の人間が全員集合したラスヴェガスで、アイズマンも初めて買い方の人間と相まみえる。信じられない虚飾の宴の只中で、正気なのはどちらか
要約
リップマンは新しい問題を抱えていた。アメリカの住宅価格は下落し、サブプライム・ローンの不履行率は上昇しているのに、どういうわけか、サブプライム・モーゲージ債は堅調で、その債券に対する保険料にも動きがなかった。
今やリップマンは実質的に、100億ドル分のサブプライム・モーゲージ債をショートしていて、期限のわからないプレミアムを年間1億ドル支払っていた。
この時点で、リップマンの博打を支えていたのは、アイズマンのようなCDSの売買に料金を支払ってくれる顧客の投資家だったが、そういった投資家はすでにやる気を失いつつあった。
中には、ウォール街がCDSの償還を防ぐために、サブプライム・モーゲージ債市場を操作しているのではないかと疑う者もいた。
リップマンは、自分と同じ側に立つ仲間を必死でかき集めていたが、今やその仲間たちが離散しつつあった。そして、アイズマンまでもが離れていくのではないかと、リップマンは案じていた。
CDOマネジャーという職業
〈オカダ・レストラン〉の鉄板焼きの間にはテーブルが4卓あって、それぞれにリップマンに口説かれてサブプライム債をショートしたヘッジファンド・マネジャーが1人と、同じ債券をロングしている投資家たちが同席するようになっていた。
アイズマンの席の両側には、リップマンと、ハーディング・アドヴァイザリーという投資会社の経営者、ウィン・チャウと称する男が座った。
のちのち、アイズマンが金融危機の起源について話すときは、ウィン・チャウとの会食の話から始めるのが習いとなった。チャウは、およそ150億ドルの金を、モーゲージ債のトリプルBのトラッシュに裏付けされたCDOだけに投資していた。
AIGが市場を去った今、主な買い手はウィン・チャウのようなCDOマネジャーになった。
フロントポイント・パートナーズは、その貸し倒れ率がすでにウィン・チャウのポートフォリオを丸ごと消し去るだけの数値に達していることを知っていた。
CDOマネジャーの仕事は、ウォール街の投資銀行を選定して、投資家たちに債券を吟味させることだ。それに加えて、各CDOに含まれるおよそ100のサブプライム債を監査し、質の悪いものが値下がりする前に、質の良いものと入れ替えること。
とはいえ、現実には、ウィン・チャウに出資してトリプルAのトラッシュを買った投資家は、絶対安全で損をする心配がなく、監査の必要も、場合によっては真剣に考える必要すらない証券だと考えていた。
CDOマネジャーは10億ドル単位の金を託してくれる大口投資家に対して、顧客のことを何より優先する姿勢を示すため、サブプライム・ローンが債務不履行に陥った際に、真っ先に消滅してしまうものを自分で所有し続けた。
一方で、投資家の誰一人、わずかな金も目にしないうちに、0.01%の手数料をかすめ取り、投資家に元利を払い戻す際にも、同じくらいの手数料を資金の底から抜き取るという旨みもある。
ほとんど手間もかけず、経費もなしで、何百億ドルもの金を運用するのだから、「濡れ手に粟」の莫大な収入になる。
アイズマンは言う。「CDOを扱った経験もない人間にCDOのポートフォリオを運用させるなんて、仕組み債の市場はどこまで狂っているのかと、開いた口がふさがらなかったよ」
チャウの実際の仕事は、チャウが“雇った”と豪語する投資銀行の看板をチラつかせ、客を呼び込むことだった。実際に、投資家たちは、たとえメリル・リンチが運用していなくとも、メリル・リンチ印のCDOを買いたがった。
アイズマンにも、ようやくこの業界の狂乱ぶりが飲み込めた。今、アイズマンは、自分が買ったCDSの向こう端にいる生身の人間と、直に顔を合わせていた。そして、腑に落ちた。
CDSトレードの相手方にいるのが詐欺師か暗愚の徒であることを心得させるために、リップマンが選んだのがウィン・チャウだった。
チャウはアイズマンに、自分の手数料は取扱い高に準じるので、全く何もないよりは、粗悪なCDOを500億ドル持つ方がましなのだと語った。
また、一番の懸念は、アメリカ経済が活気を帯びてきて、ヘッジファンドがサブプライム・モーゲージ市場の下落に大きく賭けるのをためらうことだと打ち明けた。
食事が終わるやいなや、アイズマンはグレッグ・リップマンを捕まえ、ウィン・チャウを指差してこう言った。
「この人が買っているものをショートしたい。どんな証券でも」
そんな恐ろしいことが起こるわけはない
チャーリー・レドリーとベン・ホケットはベネチアン・ホテルのロビーをうろうろしていた。
2人は様々な人に会って話をすることで、自分たちが“間違っている”理由を説明してくれる人を見つけたかった。
しかし、市場関係者たちはコーンウォールの投資哲学に賛同しなかったが、説得力のある反対意見を述べようともしなかった。
関係者がサブプライムCDOを擁護する際の中心的な主張は、短いその歴史の中で、憂えるべき規範の不履行は一度も起こっていないというものだった。
サブプライム・モーゲージ市場における仲介機関は、統計上は意味のない過去の実績をもとに、未来を予測することによって、自らを欺いていた。
3ヶ月前、初めてサブプライムCDOのダブルAのトラッシュに対するCDSを1億ドル分買った時、コーンウォールは、起こりそうもないできごとに少額の金を賭けたつもりでいた。
しかし、サブプライム市場を動かしている人々の話を聞けば聞くほど、ダブルAの債券の急落が、万一の事態などではなく、十分に起こりうることだと思えてきた。
そこにいる連中がサブプライム・モーゲージ市場の崩壊をありえないことと決めつけているのは、もしそれが起こったとしたら大惨事になるからであり、そんな恐ろしいことが起こるはずがないと思い込んでいるだけだった。
格付け機関の人間は何も知らない
アイズマンは20年近くウォール街で働いてきたが、ほとんどの株式市場関係者と同じく、ムーディーズやS&Pの人間と同席したことはなかった。株式市場の人間は、格付け機関の存在をあまり意識することがない。
今、アイズマンが初めて格付け機関の人間と言葉を交わして、強く印象付けられたのは、社員たちの覇気のなさだった。
業界全体が格付け機関の支えによって発展してきたというのに、格付け機関で働く社員たちは、ほとんど業界の一員とはみなされていなかった。
アイズマンが格付け機関の実情を認識したのも、ヴェガスでのことだった。こちらが気にしていることについて、格付け機関はまったく無頓着だった。
格付け機関がもっぱら気にしているのは、投資銀行から依頼される格付けの件数とその手数料をできる限り増やすことだった。
かつて非公開企業だったムーディーズは2000年に株式を公開し、以来、その売上高は、2001年の8億ドルから2006年の20億ドルへと急上昇することになる。増収のかなりの部分は、仕組み金融として知られる、難解な住宅資金部門から発生していた。仕組み金融業者を引きつける最も確実な方法は、仕組み金融業界が立てた見通しを受け入れることだ。
ダニエルは言う。「すべての相手に同じ2つの質問をしました。住宅価格についてどんな見通しを立てているのか。そして、ローンの貸し倒れについてどんな見通しを立てているのか、です。」
2大格付け機関は、どちらも、住宅価格は上昇し、ローンの貸し倒れ率は5%前後になると考えていた。それがもし正しいとすれば、その土台から創られた証券は、たとえ最低格付けのトリプルBのサブプライム・モーゲージ債でも儲かる商品ということになる。
アイズマンがあきれたのは、ラスヴェガスで会った人間全員が、なんの葛藤も抱えていないように見えたことだ。自分たちのしていることを、深く考えず、ただやっているだけだった。
格付け機関の質は業界にとどまれる最低線すれすれまで落ち、そこで働く社員は、自分たちがどれだけウォール街の大手投資銀行に利用されてきたか、気づいてもいないありさまだった。
3人がラスヴェガスに出発したとき、サブプライム・モーゲージ債のショート分の持ち高は3億ドル強だった。帰ってきたとき、その額は5億5,000万ドルになっていた。
運用資本は5億ドルなので、持ち高がポートフォリオを大きく上回った。
しかし、3人はまだ止めなかった。オフィスに戻った初日、ムーディーズの株を1株73.25ドルでショートし、しかるのちに、ウィン・チャウのような、トレードの相手方となる新たな企業、新たな人物探しに取りかかった。